チイクラフォーラム10
THE NEXT STAGE
その時を駆け抜けよう!
2025(令和7)年9月19日(金)20日(土)
会場 ソニックシティ 小ホール

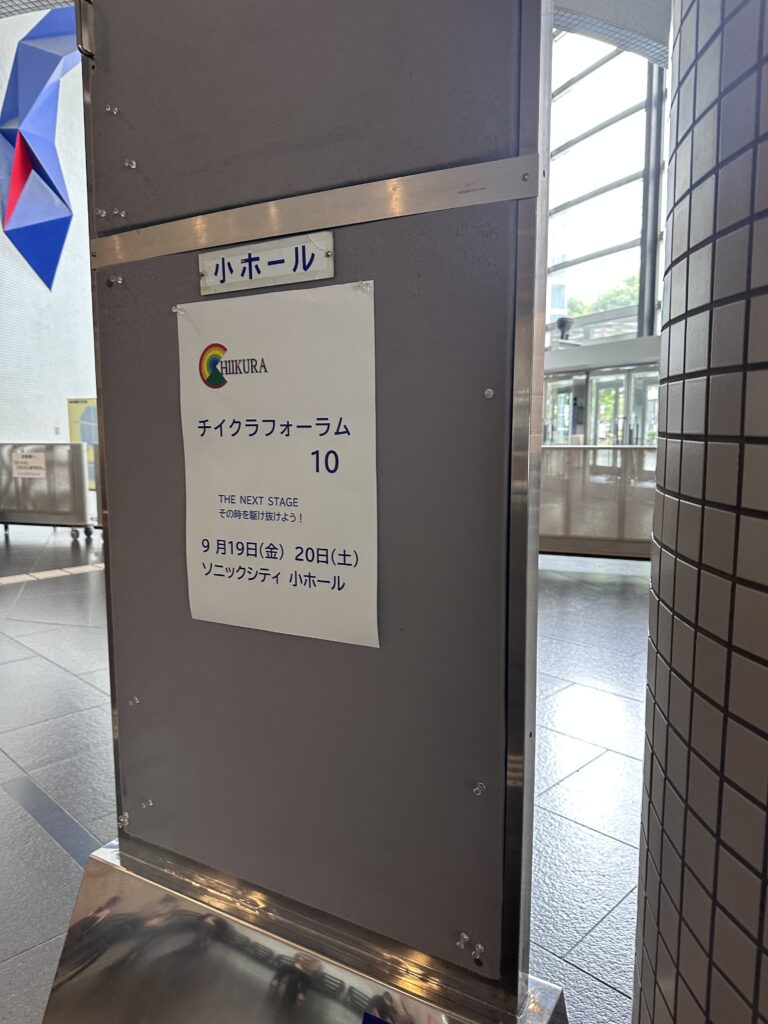
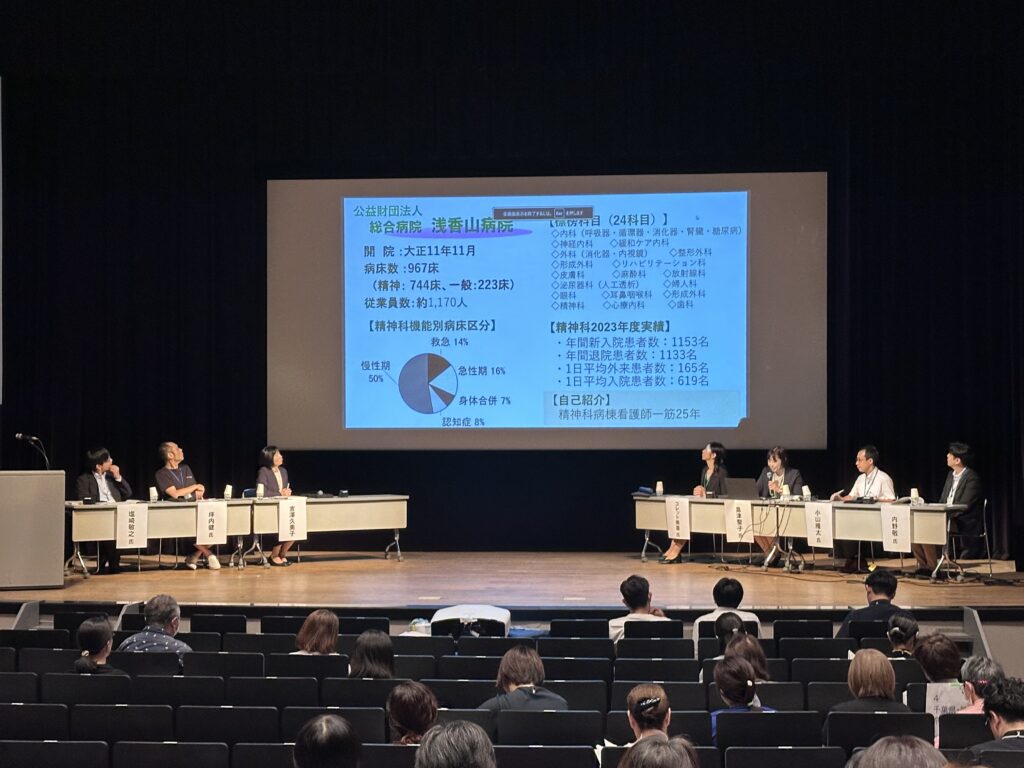
はじめに
9月18日木曜日の夜、藤並駅から夜行バスに乗り込みました。初めてのチイクラフォーラム。期待と少しの不安を胸に、大宮駅へ向かいます。
翌朝、秋を感じる涼しさの中、大宮駅に到着。しばらく時間をつぶしてから会場受付へ。そこで、偶然にも澄田さんに遭遇。知っている方の顔を見て一気に緊張がほぐれました。
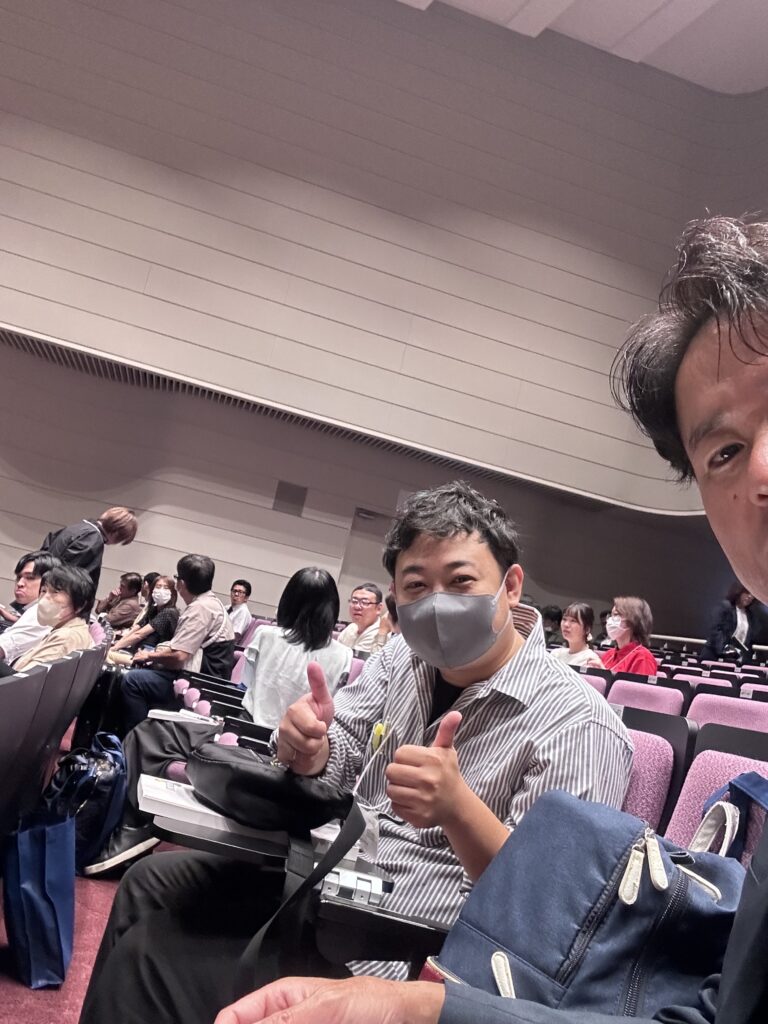
さらに、宮本病院の中野さん、片野田さん、岩橋さんとも再会。これまで研修や地域活動支援センター(地活)視察でお世話になった方々に再びお会いでき、心強さを感じながら二日間をスタートさせました。
参加の印象
二日間はあっという間で、学びと刺激に満ちた濃密な時間でした。
「次のステージへ進むために何が必要か」を、現場と行政の両面から考える機会となりました。
今回の特筆点
参加レポートだけでは伝えきれない学びの中で、特に印象に残ったのが地域生活支援拠点づくり。
そこで、フォーラムで学んだ半田市の取組を中心にまとめ、
「半田市の事例を学び 有田圏域の拠点づくりを次のステップへ進める」
と題したレポートを以下のとおり作成しました。ぜひ併せてご覧ください。
「半田市の事例を学び 有田圏域の拠点づくりを次のステップへ進める」
1. 取組の背景と課題認識
- 市の概要
- 愛知県半田市:人口約12万人。障害福祉サービスや地域生活支援事業の利用者も多い。
- 既存の拠点機能の限界
- 以前から地域生活支援拠点としての基本機能(緊急時の一時預かり、24時間相談等)は整えていたが、専任の拠点コーディネーターが不在。
- そのため、事業所や家族からの細やかな要望・緊急事態・地域移行などに十分対応できず、「やりたくても人手が足りず実現できない」状況だった。
- 財源確保の壁
- 市単独でコーディネーター1名を雇用する予算を確保するのは困難で、せいぜい半人分程度。
- コーディネーターの必要性は認識していたものの、実現できない状態が長く続いていた。
2. コーディネーター配置に至る経緯
- 2023年度報酬改定を契機に突破口
- 報酬改定により、地域生活支援拠点コーディネーターが個別給付(加算)として算定可能になった。
- これにより、市が直接委託費を計上しなくても、サービス報酬の中で人件費を賄える仕組みができた。
- 配置の実現
- 社会福祉法人が運営する基幹相談支援センター内に拠点コーディネーター1名を配置。
- 市は制度的後ろ盾を持ちつつ、柔軟な人材確保が可能になった。
- 運営体制
- コーディネーターは基幹相談支援センターと常に連携し、行政・相談支援・事業所を結ぶハブとして機能。
3. 組織構造と役割分担
- 半田市自立支援協議会の3つの柱
- 運営会議:協議会全体を動かすエンジン。地域課題を整理し、対応策を検討。
- 相談支援連絡会:市内のすべての相談支援事業所が加入。相談支援体制の整備や質の向上を担う。
- 事業所連絡会:市内の福祉サービス事業所が参加。人材育成、緊急時対応、サービス間のネットワークづくりを推進。
- 課題
- これまで基幹相談支援センターが3機能すべてを担っており、人手不足から十分な活動が困難だった。
- コーディネーター配置による変化
- 事業所連絡会を中心に役割を分担。
- 相談支援連絡会や勉強会なども、より計画的に開催できるようになった。
4. コーディネーターが担った主な活動(実績)
コーディネーターは、配置後わずか1年余りで以下のような成果を挙げた。
4-1 相談・連絡体制の充実
- 市内約40か所の福祉サービス事業所を1件ずつ訪問し、現場の課題や緊急対応の実態を把握。
- 顔の見える関係を構築し、相談の早期化・平準化に貢献。
- グループホームやヘルパー事業所の意見交換会・勉強会を新設。
- これまで細々としか実施できなかった勉強会や現場向け研修を複数回開催。
4-2 緊急対応の仕組みづくり
- 緊急対応プランを作成・毎年更新。
- 家族の急病、災害時、利用中断時などを想定。
- 事前に連絡先・支援手順を明確化。
- サービス未利用者も対象にすることで、潜在的な緊急リスクにも備えた。
- 緊急対応を「事後対応」から「予防的対応」へ転換。
4-3 地域移行と地域づくり
- 行政職員と病院を訪問し、長期入院中の市民の退院後の暮らしを一緒に検討。
- 退院後に必要なサービス利用計画を立て、地域で暮らせる環境整備を支援。
- その課題を自立支援協議会にフィードバックし、地域全体で解決を図った。
4-4 支援者支援
- コーディネーター配置により、基幹相談支援センターに時間的余裕が生まれた。
- 困難ケース検討会や支援者向け研修、モニタリングの質向上など、支援者への支援が拡充された。
5. 成果と効果
- 役割分散による負担軽減
- 事業所連絡会や勉強会をコーディネーターが主導し、基幹相談支援センターの業務負担を軽減。
- 地域ネットワークの強化
- 事業所訪問・意見交換を通じて、事業所同士や行政との協力体制が強化。
- 緊急対応力の向上
- 予防的な緊急対応プランや迅速なフォロー体制により、利用者・家族の安心感が向上。
- 地域移行の推進
- 長期入院者の地域移行を具体的に支援し、地域生活への移行を後押し。
6. 有田圏域への示唆
- 財源確保の工夫
- 報酬改定による加算活用は、町単独予算に頼らず人材配置を可能にする。
- 顔の見える関係づくり
- 事業所訪問や連絡会を通じて課題を早期に把握し、地域内の信頼関係を強化。
- 予防的な緊急対応プランの導入
- サービス未利用者を含め、利用者ごとに事前対応を整理することで、いざという時に備えられる。
まとめ
半田市は、財源の工夫と組織的な役割分担によって、
- 相談・連絡体制の充実
- 予防的な緊急対応力の向上
- 地域移行・地域づくりの推進
を短期間で実現しました。
この成果は、単なる「他市の成功事例」ではありません。
いま有田圏域が直面している状況――社会資源が限られ、行政が中心となって基幹相談の役割明確化と機能整備を進め、地域の相談支援体制づくりに取り組んでいる現実に、まさに重なります。
私たち有田圏域の強みは、顔の見える関係です。
これまで培ってきた信頼のネットワークは、拠点づくりを一気に加速させるエンジンになります。
半田市が示した道筋は、私たちの次の一歩を後押ししてくれます。
コーディネーターを配置し、基幹相談の担ってきた役割を分かち合うことで、地域全体が支え合い、まだ手の届かなかった人や状況にまで支援を届けることができる。
その力は、これからの有田圏域の地域生活支援拠点を動かす確かな燃料です。
さあ、私たちも動き出しましょう。
顔の見える関係を力に変え、有田圏域ならではの拠点づくりを次のステージへ――。



植草学園大学 野澤和弘さんのうしろ姿です。フォーラムではとってもいいお話を聞かせていただきました。一般社団法人スローコミュニケーションぜひご覧ください。

