医療的ケア児への支援と取り組みについて
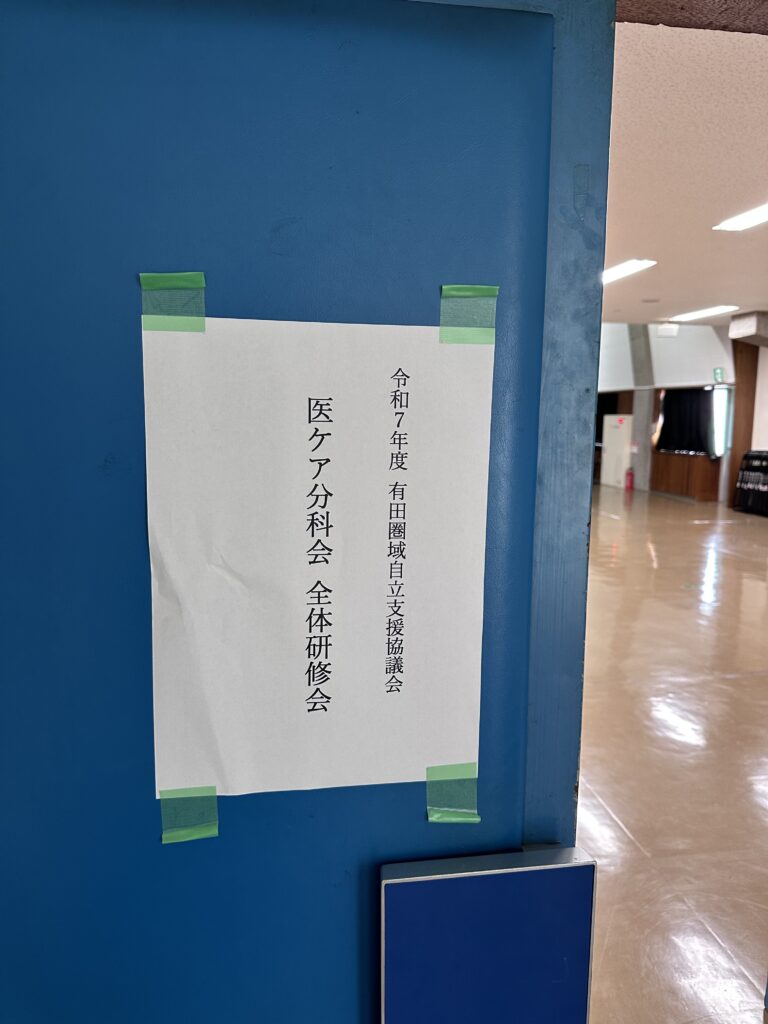

医療的ケア児への支援と取り組みについて
在宅看護センター「幹はうす」代表理事・訪問看護ステーション管理者
丸山さん 講演より
医療的ケア児支援の現場は、制度や加算の話だけでは語りきれません。
今回の研修では、在宅看護センター「幹はうす」代表理事であり、訪問看護ステーションの管理者でもある丸山さんが、日々の実践をもとに語ってくださいました。
会場に残ったのは、「重度でも、意思はある」という言葉でした。
小さな反応を“意思”として受け取る
丸山さんは、重症心身障害のある方への関わりの中で、表情やうなずきといったわずかな反応を丁寧に受け取ることの大切さを語られました。
外からは分かりにくい。
けれど、問いかけに応える瞬間がある。
その反応を「たまたま」と流すのではなく、「本人の意思」として扱うかどうかで、支援の方向は大きく変わる。
暮らしの選択も、家族の見え方も変わっていく。
支援とは、代わりに決めることではない。
決められる力を信じることから始まるのだと、静かに示されました。
家族の“限界”は見えにくい
訪問看護や預かり支援を始めた当初、保護者が子どもから離れられない場面が多くあったといいます。
帰ってもらうこと自体が難しい。
それだけ、日常が張りつめている。
ある家族が初めて子どもを預けた日、祖母が「娘がゆっくりご飯を食べている姿を初めて見た」と涙ぐんだというエピソードが紹介されました。
家族は、踏ん張ることに慣れてしまう。
外からは見えない疲労が積み重なっている。
訪問回数や時間を決めるときも、制度上できるかどうかではなく、「家族が少し息をつけるか」を軸に考えているという言葉が印象に残ります。
入浴は“活動”である
放課後等デイサービスの中で入浴支援を取り入れた経緯も紹介されました。
入浴は単なる介助ではない。
身体がゆるみ、呼吸が整い、家族の夜が少し楽になる。
「お風呂ほどいい活動はないと思っているんです」
その一言に、生活全体を見ている支援の姿勢がにじんでいました。
発達は、五感の中で育つ
講話の後半では、医療的ケアだけでなく、子どもの発達全体に視点が広げられました。
・見る力は、育てなければ伸びない
・聞く力も、経験の中で育つ
・身体感覚は、自然の中でゆっくり育つ
視力そのものではなく「見え方」によって学習や疲労が左右されること。
聴こえの特性が言葉の獲得に影響すること。
感覚過敏のある子どもに、訓練だけを強いることの難しさ。
草や泥、水といった自然の中で、嫌悪感を和らげながら感覚を育てるという実践は、医療と生活が切り離されていないことを教えてくれます。
相談は、制度より“関係”から始まる
丸山さんは、交流会やカフェといった「立ち寄れる場」の重要性にも触れました。
相談機関があっても、関係がなければ相談は起きない。
普段から顔を合わせる場所があることで、「ちょっと聞いてほしい」が生まれる。
NICU退院後の家族に、先輩家族が自然に声をかける場面。
専門職ではなく当事者の言葉が、支えになる瞬間。
地域の中に、安心して弱さを出せる場所をどうつくるか。
それもまた、医療的ケア児支援の一部だと感じました。
重度でも、可能性は閉じない
テクノロジーを活用し、重度の障害があっても働くことができる事例も紹介されました。
身体が動きにくくても、スイッチやICTを通して社会とつながる。
短時間のトライアル雇用から継続雇用へと進んだ実践は、「できない」から始めないことの危うさを教えてくれます。
最後に
医療的ケア児支援は、医療の問題だけではありません。
遊び、集団、自然、五感、家族、地域。
そして、本人の小さなサイン。
丸山さんの話は、制度の枠組みを超えて、「暮らしの線」で支援を組み立てる視点を私たちに問いかけました。
重度でも、意思はある。
家族の限界は、見えにくい。
だからこそ、丁寧に見る。
丁寧に聴く。
その積み重ねが、地域で生きる力を支えていくのだと感じた講演でした。これからを考える
在宅看護センター「幹はうす」代表理事・訪問看護ステーション管理者
丸山さん 講演より
医療的ケア児支援の現場は、制度や加算の話だけでは語りきれません。
今回の研修では、在宅看護センター「幹はうす」代表理事であり、訪問看護ステーションの管理者でもある丸山さんが、日々の実践をもとに語ってくださいました。
会場に残ったのは、「重度でも、意思はある」という言葉でした。
小さな反応を“意思”として受け取る
丸山さんは、重症心身障害のある方への関わりの中で、表情やうなずきといったわずかな反応を丁寧に受け取ることの大切さを語られました。
外からは分かりにくい。
けれど、問いかけに応える瞬間がある。
その反応を「たまたま」と流すのではなく、「本人の意思」として扱うかどうかで、支援の方向は大きく変わる。
暮らしの選択も、家族の見え方も変わっていく。
支援とは、代わりに決めることではない。
決められる力を信じることから始まるのだと、静かに示されました。
家族の“限界”は見えにくい
訪問看護や預かり支援を始めた当初、保護者が子どもから離れられない場面が多くあったといいます。
帰ってもらうこと自体が難しい。
それだけ、日常が張りつめている。
ある家族が初めて子どもを預けた日、祖母が「娘がゆっくりご飯を食べている姿を初めて見た」と涙ぐんだというエピソードが紹介されました。
家族は、踏ん張ることに慣れてしまう。
外からは見えない疲労が積み重なっている。
訪問回数や時間を決めるときも、制度上できるかどうかではなく、「家族が少し息をつけるか」を軸に考えているという言葉が印象に残ります。
入浴は“活動”である
放課後等デイサービスの中で入浴支援を取り入れた経緯も紹介されました。
入浴は単なる介助ではない。
身体がゆるみ、呼吸が整い、家族の夜が少し楽になる。
「お風呂ほどいい活動はないと思っているんです」
その一言に、生活全体を見ている支援の姿勢がにじんでいました。
発達は、五感の中で育つ
講話の後半では、医療的ケアだけでなく、子どもの発達全体に視点が広げられました。
・見る力は、育てなければ伸びない
・聞く力も、経験の中で育つ
・身体感覚は、自然の中でゆっくり育つ
視力そのものではなく「見え方」によって学習や疲労が左右されること。
聴こえの特性が言葉の獲得に影響すること。
感覚過敏のある子どもに、訓練だけを強いることの難しさ。
草や泥、水といった自然の中で、嫌悪感を和らげながら感覚を育てるという実践は、医療と生活が切り離されていないことを教えてくれます。
相談は、制度より“関係”から始まる
丸山さんは、交流会やカフェといった「立ち寄れる場」の重要性にも触れました。
相談機関があっても、関係がなければ相談は起きない。
普段から顔を合わせる場所があることで、「ちょっと聞いてほしい」が生まれる。
NICU退院後の家族に、先輩家族が自然に声をかける場面。
専門職ではなく当事者の言葉が、支えになる瞬間。
地域の中に、安心して弱さを出せる場所をどうつくるか。
それもまた、医療的ケア児支援の一部だと感じました。
重度でも、可能性は閉じない
テクノロジーを活用し、重度の障害があっても働くことができる事例も紹介されました。
身体が動きにくくても、スイッチやICTを通して社会とつながる。
短時間のトライアル雇用から継続雇用へと進んだ実践は、「できない」から始めないことの危うさを教えてくれます。
最後に
医療的ケア児支援は、医療の問題だけではありません。
遊び、集団、自然、五感、家族、地域。
そして、本人の小さなサイン。
丸山さんの話は、制度の枠組みを超えて、「暮らしの線」で支援を組み立てる視点を私たちに問いかけました。
重度でも、意思はある。
家族の限界は、見えにくい。
だからこそ、丁寧に見る。
丁寧に聴く。
その積み重ねが、地域で生きる力を支えていくのだと感じた講演でした。
